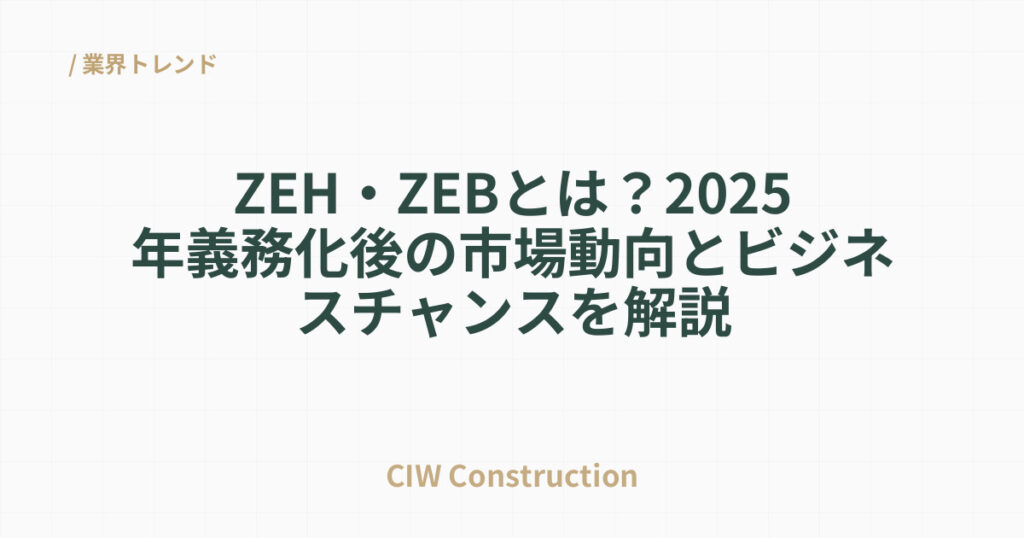「ZEH(ゼッチ)」「ZEB(ゼブ)」という言葉を目にする機会が急速に増えています。これは、日本のエネルギー政策と建設・不動産業界のあり方を根本から変える、巨大なトレンドです。
2025年4月には「省エネ基準適合義務化」が迫り、2030年に向けて基準はさらに引き上げられる方針です。この記事では、ZEH・ZEBの基本的な定義から、爆発的に成長する市場データ、主要企業の戦略、そしてこの変革期に生まれる新たなビジネスチャンスまでを網羅的に解説します。
この記事の目次
ZEH・ZEBとは?定義と国家戦略としての背景
ZEH(ゼッチ)およびZEB(ゼブ)は、単なる「省エネ建築」を超えた概念です。これらは日本の2050年カーボンニュートラル実現に向けた中核的施策であり、建築物分野(国内CO2排出量の約35%を占める)の脱炭素化の切り札と位置づけられています。
ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス) の定義
ZEHは、建物の「外皮(がいひ)」(屋根、外壁、窓など)の断熱性能を大幅に向上させ、高効率な設備(空調、給湯など)で消費エネルギーを削減(=省エネ)。残りのエネルギーを太陽光発電などで創出(=創エネ)することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支を正味(ネット)でゼロ以下にすることを目指す住宅です。
普及を促すため、エネルギー削減率や立地条件に応じて、以下の階層的な定義が設けられています。
- 『ZEH』:省エネ(20%以上削減)+創エネで、100%以上の削減を達成する理想形。
- Nearly ZEH:創エネを含め75%以上の削減を達成。都市部の狭小地などが対象。
- ZEH Oriented:創エネ設備は搭載せず、高い省エネ性能(20%以上削減)のみで基準を満たす。集合住宅などが対象。
ZEB (ネット・ゼロ・エネルギー・ビル) の定義
ZEBは、ZEHの非住宅建築物版(オフィスビル、学校、工場など)です。建築物の特性に合わせ、より細分化された階層が設定されています。
- 『ZEB』:省エネ(50%以上削減)+創エネで、100%以上の削減を達成。
- Nearly ZEB:創エネを含め75%以上の削減を達成。
- ZEB Ready:創エネは含まず、省エネのみで50%以上の削減を達成。将来のZEB化を見据えた先進的な建築物。
- ZEB Oriented:延床面積10,000㎡以上の大規模建築物で、用途に応じ30%~40%以上の省エneを達成。
政策的アプローチとしての階層構造
この階層構造は、単なる技術分類ではありません。理想形(『ZEB』)だけでは普及が進まない現実を踏まえ、まずは省エネ性能の向上(Ready/Oriented)から着手させ、最終的に創エネ設備を追加させるという、普及の障壁を段階的に取り除くための現実的な政策ロードマップが定義自体に組み込まれています。
市場動向データ分析:「2025年義務化」の影響と成長予測
ZEH/ZEB市場は、国の強力な政策(アメとムチ)に牽引され、非連続的な成長フェーズに入っています。
ZEH市場規模と爆発的な成長
株式会社矢野経済研究所の調査によると、2023年度のZEH国内市場規模(工事費ベース)は6兆5,712億円に達し、前年度比61.4%増という驚異的な伸びを記録。2030年度には14兆円、2035年度には17兆2,700億円に達すると予測されています。
この背景には、2025年4月から原則全ての新築建築物に省エネ基準適合が義務化される、いわば「2025年ショック」を控え、規制対応をビジネスチャンスと捉えた先行投資が市場を押し上げていることがあります。
| 年度 | 市場規模(億円) | 前年度比 | 内訳:集合ZEH(億円) |
|---|---|---|---|
| 2022年度 (実績) | 40,714 | – | – |
| 2023年度 (実績) | 65,712 | +61.4% | 39,427 |
| 2030年度 (予測) | 140,000 | – | – |
| 2035年度 (予測) | 172,700 | – | – |
| 出典:矢野経済研究所「ZEH(Net Zero Energy House)市場に関する調査」(2025年5月9日発表)を基に作成 | |||
特に注目すべきは、これまで遅れていた「集合住宅(マンション)」市場の急成長です。過去3年間の平均成長率は、戸建ZEHの19.1%増に対し、集合ZEHは163.5%増と、市場の牽引役が戸建から集合住宅へと明確にシフトしています。
ZEB普及の現状:新築と既存ストックのギャップ
新築市場が活況を呈する一方、既存の建築ストック(既存ビル)を含めた普及には大きな課題があります。
- 新築における普及率:2023年度の新築非住宅建築物における「ZEB基準の水準」の達成率は19.7%(国土技術政策総合研究所)と、まだ全体の2割に留まっています。
- ストック全体での普及率:既存ビルを含む非住宅建築ストック全体におけるZEB普及率は、面積ベースでわずか2%程度(環境省)です。
- 官民格差:さらに、民間建築物のストック普及率が2.0%であるのに対し、公共建築物では0.27%と、10分の1以下の水準に留まっています。
課題=ビジネスチャンス:既存ストックと公共建築物という巨大市場
この「新築の活況」と「既存ストックの低普及」との深刻なギャップは、二極化のリスクを示すと同時に、裏を返せば「既存ビルのZEB化改修」および「公共建築物のZEB化」という、未開拓の巨大なブルーオーシャン市場が存在することを示しています。
主要企業の戦略:ZEH/ZEBを核としたビジネスモデル
業界をリードする企業は、ZEH/ZEBを単なる「高性能な建物」として販売するだけでなく、新たなビジネスモデルの核として活用しています。
大手ハウスメーカー:「モノ売り」から「コト売り(サービス化)」へ
積水ハウスは、戸建住宅のZEH比率96%(2024年度)を達成するトップランナーです。その戦略が秀逸なのは、ZEHというハードウェアをプラットフォームとし、顧客との長期的な関係を構築する「サービス化」を推進している点です。
- 入居者売電方式:賃貸住宅「シャーメゾン」のZEH化(採用率77%)を進め、入居者が売電収入を得られる仕組みを提供。
- 積水ハウスオーナーでんき:卒FIT(固定価格買取制度の終了)後の余剰電力を業界最高水準で買い取るサービスを展開。
これは、製品を売り切る「モノ売り」から、エネルギーサービスなどを組み合わせた「コト売り」への明確なシフトであり、建設・不動産業界の収益構造を根本から変える可能性があります。
大手ゼネコン:先進技術のショーケースと改修市場への展開
清水建設は、2013年に日本初の『ZEB』である「生長の家 “森の中のオフィス”」を竣工。マイクログリッドによる電力自給自足など、最先端技術の実証を行う「生きた広告塔」として活用し、「ZEBのリーディングカンパニー」という強力なブランドを構築しています。
大成建設は、新築の「ZEB実証棟」だけでなく、既存ビルのZEB化にも注力。「大成札幌ビル」の改修で『ZEB Ready』を、築40年の研究所のフルリノベーションで『Nearly ZEB』を達成するなど、今後拡大する「改修ZEB」市場での高い技術力を示しています。
建材・設備メーカー:性能を支えるコア技術の競争
ZEH/ZEBの実現は、サプライチェーン全体での技術革新に支えられています。
- YKK AP:高性能樹脂窓「APW」シリーズで開口部の断熱性能をリードし、外皮性能の基準クリアに貢献。
- LIXIL:高性能断熱窓やSW工法、太陽光発電システム、節湯水栓までトータルソリューションを展開。
- ダイキン工業:省エネ性能を左右する空調設備において、高効率エアコンや全館空調で快適性と省エネを両立。
ZEH・ZEBを支える技術と未来のトレンド
ZEH/ZEBは、「パッシブ技術」「アクティブ技術」「創エネ技術」の3つの組み合わせで実現されます。
- パッシブ技術:高性能断熱材やLow-E複層ガラス、自然換気など、エネルギーを極力使わずに快適性を実現する設計手法。
- アクティブ技術:高効率空調、LED照明、高効率給湯器、BEMS/HEMS(エネルギー管理システム)など、エネルギーを効率的に使う設備技術。
- 創エネルギー技術:太陽光発電システムなど。
革新技術:ペロブスカイト太陽電池
現在、最も注目される革新技術が、日本発の「ペロブスカイト太陽電池」です。従来のシリコン系太陽電池が持つ課題を克服する可能性を秘めています。
- メリット:軽量・柔軟なフィルム状のため、これまで設置が難しかった建物の壁面、曲面、耐荷重の低い屋根にも導入可能です。また、曇天時や室内光でも発電できます。
- 将来性:エネルギー創出の機会をあらゆる建物に解放する「エネルギー創出の民主化」をもたらし、特に都市部でのZEB達成のハードルを劇的に下げると期待されます。
- 開発動向:耐久性や大面積化が課題ですが、積水化学工業などが2025年頃からの量産化・市場投入を目指し、開発を加速させています。
未来のインフラ:VPP(仮想発電所)
ZEH/ZEBは、太陽光(創エネ)、蓄電池(蓄エネ)、HEMS(制御)を標準搭載した「エネルギーセル」です。これらが地域に無数に普及すると、VPP(仮想発電所)として機能し、電力系統を支える重要な社会インフラとなります。政府や事業者が普及を急ぐ背景には、将来のVPP社会を構築するための「標準インフラ」を全国に張り巡らせるという国家戦略があります。
普及を阻む課題と、それを乗り越えるビジネスチャンス
ZEH/ZEBの普及は不可逆的なトレンドですが、そこには明確な「課題」と、それを解決する「ビジネスチャンス」が存在します。
課題1:初期コストの壁 と ファイナンスへの転換
最大の障壁は、高性能断熱材や太陽光発電などによる「初期建設コストの増大」です。しかし、この課題の本質は、単なる費用問題から「ファイナンス(資金調達)」の問題へと転換しています。
ビジネスチャンス:光熱費削減や不動産価値向上による将来キャッシュフローを評価する手法や、初期投資ゼロで省エネ改修を行うESCO事業、ESG投資の呼び込みなど、建設と金融を融合させたソリューションが求められています。
課題2:担い手不足 と 改修の技術的難易度
ZEH/ZEBの設計・施工には高度な専門知識が求められますが、対応できる設計者や中小工務店が不足しています。また、既存ビルの改修は、新築にはない制約(構造、法規制、テナント入居)があり、技術的難易度が高くなります。
ビジネスチャンス:専門知識を持つ設計者や施工管理者への需要が急増します。特に、膨大な既存ストックを対象とする「ZEB化改修」は、新築市場が縮小する中での新たな巨大市場となります。
課題3:エネルギー性能ギャップ と 運用サービス事業
設計上の計算性能と、実際の運用段階での消費量との間に乖離が生じる「性能ギャップ」が問題となることがあります。
ビジネスチャンス:BEMS/HEMSを活用して運用データを分析し、最適な運用をコンサルティングする「エネルギーマネジメントサービス」や、削減量を保証する「パフォーマンス契約」など、建物のライフサイクル全体に関与するサービス事業が重要性を増しています。
よくある質問(FAQ)
ZEH・ZEBとは簡単に言うと何ですか?
「使うエネルギー」を最小限に抑え(省エネ)、「創るエネルギー」(太陽光発電など)を増やすことで、年間のエネルギー消費量の収支を正味(ネット)でゼロ以下にすることを目指す住宅(ZEH)および建築物(ZEB)のことです。
2025年4月から何が変わるのですか?
改正建築物省エネ法により、原則として全ての新築住宅・非住宅建築物に対して、現行の「省エネ基準」への適合が義務付けられます。これにより、省エネ性能が低い建築物は新築できなくなり、ZEH/ZEB化への流れがさらに加速します。
なぜ集合住宅(マンション)でZEH化が急に増えているのですか?
2023年度の市場規模で前年度比61.4%増と急成長しました。これは、2025年の省エネ基準義務化や2030年の基準引き上げを見据え、大手デベロッパーがZEHマンションの標準化を一気に推進しているためです。
初期コストが高いのに、なぜ普及するのですか?
「ムチ」(2025年省エネ基準義務化)と「アメ」(各種補助金制度)という国の強力な政策推進が最大の理由です。加えて、光熱費削減、快適性向上、災害時の電力確保(レジリエンス)、そして「エネルギー性能」が不動産価値の新たな評価軸となり、資産価値向上に繋がるという認識が広がっているためです。
「ペロブスカイト太陽電池」とは何ですか?
日本発の次世代太陽電池技術です。軽量・柔軟で曲面に貼ることができ、曇りでも発電効率が高いのが特徴です。これまで設置が難しかったビルの壁面などにも導入できるため、都市部でのZEB化を加速させる切り札として期待されています。
まとめ:不可逆的なトレンドへの対応戦略
ZEH/ZEBの普及は、一部の先進企業だけの動きではありません。①政府(法律・政策による強力な推進)、②業界団体(自主目標の策定)、③市場(客観的データによる成長性の証明)という、「産・官・学(市場)」の三位一体の構造が強力な推進力を生み出しています。
これは、個別の課題はありつつも、ZEH/ZEBが建築のスタンダードになるという大きな流れが、もはや後戻りできない「不可逆的なトレンド」であることを示しています。
この変革期におけるビジネスチャンス
このトレンドは、建設・不動産・エネルギー業界に新たなビジネスチャンスをもたらします。
- 高付加価値化と差別化
ZEH/ZEBという明確な付加価値を提供し、他社との差別化を図ることで、受注単価の向上が期待できます。 - 既存ストック・改修市場の開拓
普及率がわずか2%の既存ストック(既存ビル)のZEB化改修は、新築市場が縮小する中での巨大なブルーオーシャン市場です。 - エネルギーサービス事業への転身
PPAモデルやVPP事業への参入により、建設会社は単なる「請負業者」から、エネルギーインフラを運営する「サービスプロバイダー」へと転身し、継続的な収益源を確保する道が開かれます。